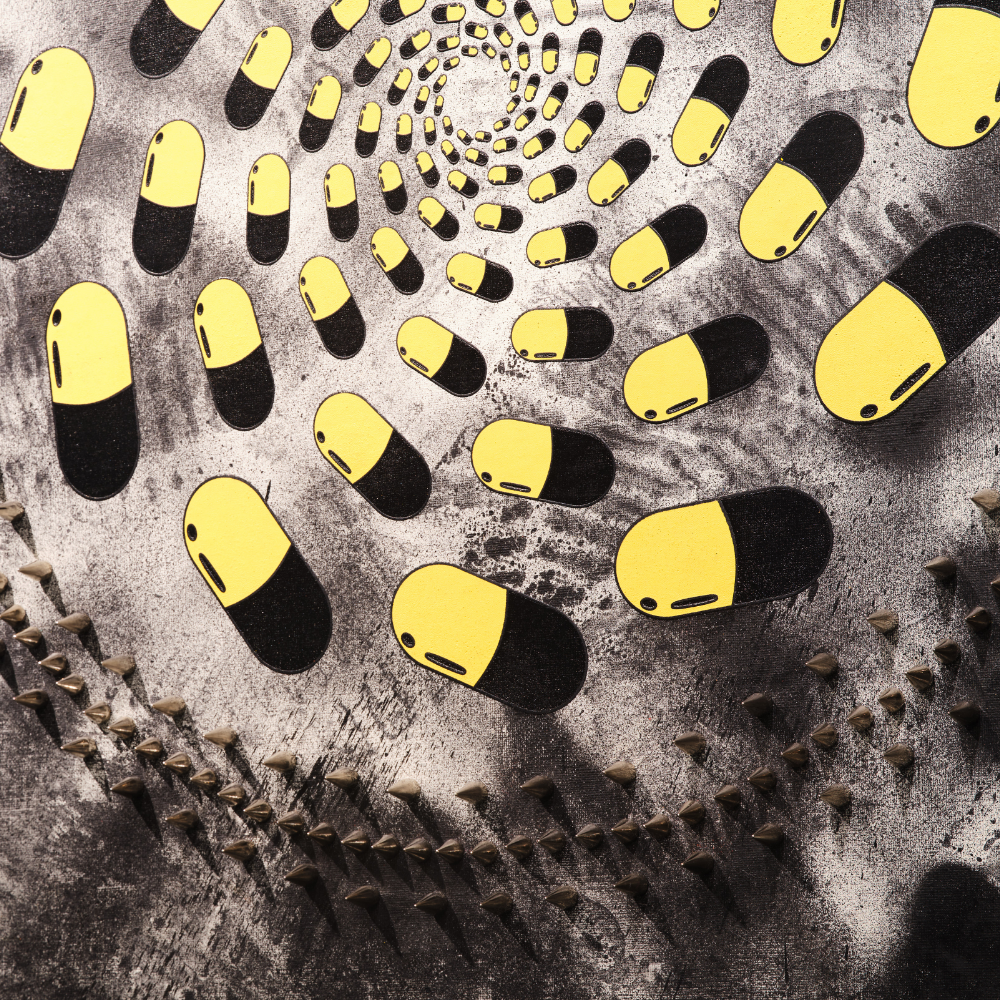洋楽三昧の幼少期。
「子供の頃はとにかく落ち着きがなく、目立ちたがり屋で人と同じことをするのがあまり好きじゃなくって、自分で流行っているものとか、かっこいいものを見つけに行くタイプでした。青森県八戸市の出身なんですけど、親父が、米軍基地が近くにある街でビリヤード屋兼喫茶店みたいなお店をやっていて、それこそMTVが流れているみたいな。それもあって、スティーヴィー・ワンダーとか当時流行っていたディスコミュージックとかソウルミュージック、ポップス、ロックなど、洋楽に自然と触れる環境で育ちました。その影響があってか、幼稚園の頃から“レコードが欲しい”って言うような音楽大好きな子供でした。最初に好きになったのはSex Pistols。何を歌っているのかはわからなかったけどめちゃくちゃカッコいい! と思って初めてCDを買いました。同世代の周りの子が邦楽を聴いているのを横目に自慢げに洋楽を聴いてましたね(笑)」
そうして、小学校、中学校と、洋楽三昧の日々を送るなかで、当時テレビ放送されていた「天才・たけしの元気が出るテレビ!!」のコーナー「ダンス甲子園」で流れるダンスミュージックの影響もあり、どんどんヒップホップの沼にはまっていくことになる。
「小学6年生の頃にはDJをやりたいって思ってましたね。それは、パブリックエネミーを見たときに、彼らのあまりのカッコよさに衝撃を受けて。そこからだんだんとラップにも興味が出てきて、海外だけじゃなくて、MICROPHONE PAGERとか日本にもカッコいいラッパーがたくさんいるのを知って、中学生の頃からはアメリカのヒップホップを聴きながら日本語ラップをやるようになりました。高校の入学祝いに親父にターンテーブルを買ってもらったんですけど、その頃はもうヒップホップにどっぷりですね。高校には野球の特待生で入学したんですけど、高校1年の夏には野球部を辞めて毎週クラブ通い(笑)。先生に“野球やらないなら1回でも赤点を取ったら即退学”って言われていたので必死に学業と両立してなんとか卒業しました」
漠然と東京に出てヒップホップで飯を食っていきたいという思いを胸に18歳で上京。錦糸町の小さな町工場で働くも、100%ヒップホップに関わる仕事がしたくて半年足らずで辞めることに。
「当時のレコード屋とか洋服屋ってめちゃくちゃ人気のある職種だったので、アルバイトの応募があってもすぐに締め切られることが多くて。結果としては、憧れだったCISCO(RECORDS)で雇ってもらえることになったんですけど、入るまでは、住む所もなくなって……友達の家を転々としながら10代にしてホームレスになったこともありました(笑)。CISCOではいろんな音楽をたくさん教えてもらいましたし、いろんな現場に遊びに行かせてもらいました。DJやラッパーがたくさん集まってくるから仲良くなれたし、自分のラップのテープを配ったりもしました。ラッパーとしてやっていくには最適の環境でしたね。で、CISCOで働いているときに初めてカメラを買うんですけど……」
CISCOで働きはじめて、朝から晩までヒップホップ漬けの日々を送るcherry chill will.に、人生のターニングポイントがやってくる。
「25歳で結婚して一人目の子供が産まれて、28歳のときに二人目が生まれたんですけど、生まれて1ヶ月後にいきなりCISCOが倒産することになって。もう唖然とするしかないですよね。貯金もないし子供が2人いて無職になって“これからどうすんだ!”って。マジで頭を抱えて悩んでたときに、それまでちょこちょこ僕が写真を撮っているのを知っていたラッパーのRYUZO君から“ライブあるから息抜きがてら遊びに来て写真撮れば?”って誘ってくれたんです。そのライブを写真を撮った時に肉眼では見ることのできないエネルギーがファインダー越しに見えてしまった瞬間があったんですね。もう完全に心を奪われてしまって。そこからはもう取り憑かれたように、毎週のようにライブ写真を撮らせてもらったり、クラブに遊びに行ってひたすらいろんな人を撮ってましたね」
高校を卒業して上京。約10年間のCISCO時代を経て、30歳にしてフォトグラファーとしての道を歩み出したcherry chill will.。現在44歳。もはやヒップホップアーティストで彼を知らない人はいないと言っても過言ではないだろう。そんな彼が考える写真との向き合い方とは。
「思えば、駆け出しの頃からやりたくない仕事はやってこなかったですね。やっぱり撮りたいのはアーティストで、パーティスナップじゃない。そんなことを言い続けたら“ライブだけでいいです”っていうオファーしか来なくなりましたし(笑)。あと、写真ってうまさじゃないから。デジタルだとパッションが出ないとかいう人もいるんですけど、そんなことは絶対ないと思っているし、いいカメラ使っているからどうのっていうのは絶対ないと思うんです。相手への信頼や尊敬から生まれる衝動っていうか、純粋に撮りたいって気持ちをずっと持ち続けて撮影していますね。現場は俺にとって遊びの延長にある居場所。別に俺自身が評価されたくてやってるんじゃなくて、10年後くらいにアーティストが“こんな時代あったな”、“このときこう思ってやっていたな”とか、ふとしたときに“あのときcherryさん居たな”って言ってくれたりするのが嬉しかったりするから。そんな風にアーティストに思ってもらえるのが一番好きですね。まさに愛とリスペクトですね」
cherry chill will.の作品を見たことがあるなら、モノクロの世界観が強く印象に残っている人も多いだろう。そこにも彼なりのこだわりがあった。
「そもそもモノクロって、写真とか映像でしか見れないじゃないですか、肉眼はカラーなので。原体験は昔の映画になるんですけど、子供の頃からモノクロの世界が好きで、この色はどんな色とか、背景はどんな色なのかなって自分で想像するのも好きだったし、どこか時代とか時間とかも全部超越するような気がするんです。もちろん、ただ自分がすごい好きだからかもしれないですけど、シンプルに画の力だけを見せられるのってカラーよりモノクロなんじゃないかなって思うんですよね。色がないということは、余白があるということ。見る人に考えさせたいんです」
憧れから日常へ。
幼少期から洋楽に触れながら、さらに最初に好きなったアーティストがSex Pistolsだったこともあり、常に身近に存在していたドクターマーチン。きっかけはパンクへの憧れだったが、現在はもはや音楽的な文脈としてだけでなく、ワークブーツとしての耐久性や英国気質溢れるデザイン性など、より日常靴として愛用しているという。
「実は今回このお話をいただいたときに“やっと来たか!”って(笑)。最初のドクターマーチンは、中2のときに買った8ホールのホワイト。高校の入学式も鉄板入りのドクターマーチンを買ってもらって、それを制服に合わせてました。コテコテのヒップホップのスタイルをしていた時期もあるんですけど、定期的にずっと変わるというか、ブーツ履きたくなるとドクターマーチンっていう。入りはパンクでしたけど、今でも普通に買っていて、家に10足以上ありますね。とくにウイングチップが大好きで、ライブの撮影でいつも履いてますし、ソールがすり減りすぎて、ストックとしてもう1足持っているくらいです。先日もお店に行って、家族分を大量買いしました(笑)。僕の中では、スニーカーかドクターマーチンかの2択しかないですね。冠婚葬祭もドクターマーチンですし」
スパイスとしてのアイテム。その象徴がドクターマーチン。
仕事もプライベートも足元はドクターマーチン。そうさせる理由はどこにあるのだろうか。
「たぶんイングランドっていうところに繋がるのかなって思うんですけど、ベースとしてイギリス的なもの、ヨーロッパ的なものが好きなんだと思います。アメリカ的なものも好きなんだけど、スパイスとしてのヨーロッパ的なものっていうのは、僕の中ですごくオシャレだったりするんですよね、昔から。その象徴が僕の中ではずっとドクターマーチンなんですよ。服はアメリカンスタイルなのに、足元にサラッと合わせると、すごくスタイリッシュになるみたいな。おそらくここ3、4年は、ほぼドクターマーチンしか履いてないから、たまにスニーカー履くと周りから珍しいですね!って言われるくらい。ライブの撮影って移動は多いし、変な体勢になったりで、スニーカーの方が絶対楽で良いに決まってるんですけど、あまりにもドクターマーチンを履きすぎて、これが一番楽なんですよね。実際ソールのすり減った感じも好きで、自分で毎回磨くんですよ。そういう作業も好きだったりして、さらに愛着も湧くっていう。僕にとってなくてはならないものですね」